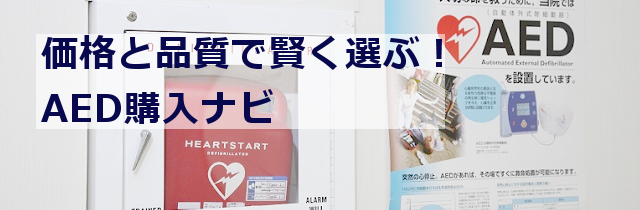-
<注目コンテンツ 1>
購入vsレンタル どっち? AEDを「購入」した場合と「レンタル」した場合の5年間のトータル価格を算出してみました -
<注目コンテンツ 2>
AED選びのポイント AEDは厚労省認可製品のみ販売されるので品質の差はないはずですが… 注意点をまとめました -
<注目コンテンツ 3>
AEDの導入事例・救命事例 設置の理想は100mおきとも言われるAED。企業や施設の導入事例と救命できた事例をご紹介
学校・自治体
このページでは教育施設や自治体の施設などへのAED導入事例を紹介します。また、補助金が受けられるかどうかについても説明します。
補助金でAEDを設置
教育施設や自治体の施設などのAEDの導入は顕著です。行政の責務として設置が求められているからです。
自治体の施設である教育施設とは、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、大学など。お子さんから教育者である大人、保護者、職員などが出入りする場所です。
自治体の施設とは交番や消防署、教育施設のほかに役所や図書館、児童館、公民館、自治体が運営するホール、プール、公園、福施施設などが含まれます。
どちらも多くの人が訪れる場所ですから、AEDの導入は必要となります。また厚生労働省のガイドラインでは交番や消防署は「人口密集地帯にある公共施設は、地域の住民の命を守るという視点から、施設の規模の大小、利用者に関わらず、AEDを設置することが望ましい」としています。
AEDは自治体が主導して導入されることが多いため、民間機関よりも設置はかなり進んでいます。また、こういった施設に対しては補助金を交付している自治体が多く、申請が通れば補助金の受給ができます。審査は厳しいものではないため、補助金を利用してAEDを設置しているところが多くあるようです。
AEDの設置・導入事例
例えば保育園・幼稚園や小学校の場合は、園児や生徒にも使用できるよう、小児用パッドが整備されているAEDが導入されています。
もちろん、大人に対しても使用できる大人用バッドもついているものです。施設の入り口など、目立つ場所に置かれていることが多く、持ち運びにも便利な計量タイプが人気です。
教育機関や自治体での救命事例
それでは自治体の施設や教育機関での救命事例を見てみましょう。
- 大学のグラウンドでフットサルのボールを胸に受けた18歳の学生が心停止に。大学内に設置されていたAEDを学生が行い、救命に成功した。
- 高校の70歳の職員が心筋梗塞で突然倒れ、教職員がAEDによる処置を実施。男性はおよそ2週間で退院。
- 区立体育館でバドミントンの試合を行なっていたところ、選手の男性が心肺停止に。体育館の浣腸がAEDの処置を行なって呼吸が回復した。
- 運動公園でテニスをしていた男性が心停止に。公園内のAEDを居合わせた女性看護士が作動させ、救命措置を実施して救命した。
- 県の施設でスポーツ大会が開催された際、60代男性が心肺停止。救護班や大会関係したによってAEDによる処置が行なわれ、救命した。
- 市民プールで70代の男性が心肺停止となり、スタッフがAEDによる処置を行い、救命に成功。
- 専門学校の女子寮で20歳の女性が倒れ、同級生たちがAEDなどの処置によって救命した。
教育機関や自治体ではAEDの導入が進んでいるため、救命の事例も多く見られました。

日本では、年間6万人もの方が病院外で心臓突然死に陥っています。救急車の平均到着時間は8分後。しかし、救命処置が1分遅れるごとに死亡率は10%も高くなってしまうのです。
このサイトは、命を救うAEDについて、価格をはじめ、販売会社や導入事例など、いま役に立つ情報をまとめました。